【まいど大阪「春のプチ車音祭」2025 & 6th New Style Meeting Sound Park in 神戸総合運動公園】開催イベントについて★★★
● お知らせ
エントリー受付期間:2/10(月)~2/24(月)まで
《注意》
今年度よりエントリーシート送付先及び振込先が変更になっておりますのでお間違えの無いようにお願い致します。
エントリーシート送付先: zextp953@yahoo.co.jp
※エントリーシートは基本メール添付にて送付をお願い致します。メールにて送信不可能な場合はFAX(0774-21-4441)でも受付可能ですが受付確認が遅れる場合がございますのでご了承下さい。
☆☆エントリーに関するお問い合わせは☆☆
TEL072-265-1184イースト担当藤原まで
エントリー代振込先:関西みらい銀行 堺支店(普通)0024668 カ)アイテイシー
会場はこちら
※審査順は先着順ではなく抽選になりますので搬入開始時間(AM8時)より早く到着されても会場入口にて並ぶのはお控え下さい。
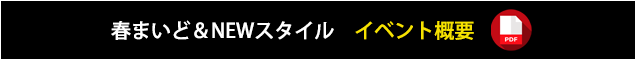
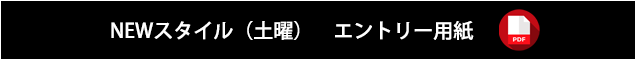





サウンドコンテスト
※評論家各クラスのみ先着20台になります。
※システム金額が150万を超える内蔵アンプ車両はシステム金額に見合ったクラスにエントリー下さい。
※複数エントリーで同一審査員の場合、審査は1回となりますのでご了承下さい。
※各金額別クラスのジャッジはエントリー締切後に発表になります(ジパング道祖尾さん、サウンドフリークス佐藤さん、イングラフ木村さん)。
★Sound Contest Class★★★サウンドコンテストクラス
-
【★ エキスパートクラス】 30台
- 評論家の先生3名の審査 初参戦でもエントリー可能
- ※CDもしくは、CD音質データのwavファイル、ハイレゾもOK
- 【審査委員】小原先生、山之内先生、土方先生【トロフィー本数】 10本
-
【★ 評論家クラス】※評論家各クラスのみ先着20台になります。
- 評論家の先生1名の審査 初参戦でもエントリー可能
- ※CDもしくは、CD音質データのwavファイル、ハイレゾもOK
- 【審査委員】 小原先生、山之内先生、土方先生のうち1名の先生【トロフィー本数】 各10本
-
【★ Aクラス】 30台
- 車両システム金額が300万円以上の車両
- ※CDもしくは、CD音質データのwavファイル、ハイレゾもOK
- 【審査委員】 サウンドフリークス佐藤さん【トロフィー本数】 10本 【★ Bクラス】 30台
- 車両システム金額が150万以上300万円未満の車両
- ※CDもしくは、CD音質データのwavファイル、ハイレゾもOK
- 【審査委員】 イングラフ木村さん【トロフィー本数】 10本 【★ Cクラス】 30台
- 車両システム金額が150万円未満の車両
- ※CDもしくは、CD音質データのwavファイル、ハイレゾもOK
- 【審査委員】 ジパング道祖尾さん【トロフィー本数】 10本
課題曲(全8曲)上2曲がまいど大阪課題曲です
 |
アルバム: | Good Luck, Babe! | ||
| アーティスト: | Chappell Roan | |||
| トラック: | Track1 : Good Luck, Babe! | |||
| https://www.qobuz.com/jp-ja/album/good-luck-babe-chappell-roan/c15g8kbko8ajc | ||||
●聴きどころ(小原先生)
弾むような楽しい8ビートでは、キックドラムの音が重くなり過ぎず。躍動的なリズムが先導するように鳴らすのが大事だ。そこにリンクするベースラインも骨太ではあるものの、軽快さも感じられる。そうしたビートを下敷きに、チャーミングなヴォーカルがフワッと広がる。特に声の高域の抜けをクリアーに再現するようにしたい。
音像は過度に絞り過ぎることのないよう、適度な膨らみを感じさせるフォルムがベター。歌詞の内容からして、「ウーム、とにかく幸運を祈るよ」といったような、仲の良い友人に向けたさり気ない応援歌だけに、楽しくリズミカルなムードが肝心だろう。
●聴きどころ(山之内先生)
シンプルな8ビートを刻む低音の立ち上がりが遅れたり余分に音を引きずると曲調とは真逆の重いリズムになってしまうので要注意。ベースの音域までアタックが遅れないことを意識しながらキレの良いリズムの再現を狙う。キーボードとヴォーカルが入ってからもベースラインが正確に聴き取れるように低域の音色と音量をコントロールできるかどうかがカギを握る。
曲の後半で音数が増えても歌詞が明瞭に聴き取れるように混濁のないサウンドを目指してほしい。声のイメージは大きめだが、左右に広がりすぎることは避けたい。エコーが上方に抜けるような広がりをイメージすると良い。
●聴きどころ(土方先生)
イントロのキックドラムの表現で、低音域のボリューム感(帯域バランス)が把握できる。シンセサイザーの音色は80年代を意識したもので、シャープさやスピード感よりも、色彩の豊かさとふくよかでレトロな質感を重視したい。
以前から話しているように、これらの要素をしっかりと表現するには、癖のない帯域バランスが最初に求められるポイントだ。続くボーカルは、適度なリバーブがかかっており、口元が極端にコンパクトではないものの、定評のあるパワフルな歌唱力をしっかりと伝える芯の強さが求められる。
0:37からコーラスが加わり、ベースの存在感が増すことで楽曲が盛り上がる。このとき、左右のスピーカーの間に浮かび上がるコーラスの位置関係も重要な聴きどころだ。チャペル・ローン がここへきて評価された理由の一つは、どこか懐かしさを感じさせるメロディと、それをブーストする力強いボーカルの歌い回しにあると僕は考えている。「女の子同士の恋愛を描いた」この楽曲を、メロディアスに表現したい。
昨年開催されたホームオーディオのショーでは、このアーティストの楽曲をデモで使っていたので、個人的にも思い入れがある。
 |
アルバム: | アンドリス・ネルソンス / ショスタコーヴィチ:交響曲第2・3・12・13番 | ||
| アーティスト: | ボストン交響楽団・アンドリス・ネルソンス | |||
| トラック: | Track10 : Symphony No. 12 in D Minor, Op. 112 "The Year 1917" - IV. The Dawn of Humanity (L'istesso tempo) | |||
| https://www.qobuz.com/jp-ja/album/shostakovich-symphonies-nos-2-3-12-13-andris-nelsons-boston-symphony-orchestra/rlxkusnir0ata | ||||
●聴きどころ(小原先生)(6分過ぎから10分過ぎ辺りまでを試聴予定)
当初は「レーニン交響曲」という着想であった第12番だが、結果的にはその革命家の生涯を描く構想から変容し、「十月革命」をテーマとして作曲された。その第4楽章は「人類の夜明け」という標題が付けられており、共産党入党の忠誠の証として提出された意図があるとされるが、ショスタコーヴィッチの本意でなく、彼ならではのアイロニーが巧妙に曲想に刷り込まれている。
目まぐるしい展開の木管のアンサンブルと弦楽隊の重奏が、クレッシェンドしていく過程でダイナミックに描かれる。ここをいかにがっちりと、堅牢な響きの骨格を維持して再現するかが腕の見せ所。ティンパニーやスネアドラムの主張の強いリズム、大太鼓の屈強な一撃などを経て、終結に向かってファンファーレのような歓喜へとなだれ込む勢いをパワフルに表現することが望まれる。
●聴きどころ(山之内先生)(6分05秒から9分前後までを試聴)
十月革命をテーマに書かれた標題音楽であり、第4楽章は「人類の夜明け」を讃える勝利の音楽ととらえることができる。ホルンで提示される勝利の主題とのその変奏が中心をなすが、木管や弦楽器がめまぐるしく動き回るもう一つのテーマが交錯して次第に盛り上がり、高揚した気分のなか終結にいたる。試聴する箇所は終結部に向けて音楽が動き出す部分で、弱音からフォルティッシモに向かうクレッシェンドの力強さ、決然としたティンパニの強打、鮮明なリズムを刻む小太鼓など、重要なフレーズを的確に再現することがポイントだ。
ヴァイオリンが高音域で繰り返す旋律や大振幅の大太鼓など、ショスタコーヴィチならではの楽器の使い方が本来の効果を発揮するように明晰かつ壮大なサウンドを狙いたい。
●聴きどころ(土方先生)(試聴するパートですが、5分45秒から9分前後までとさせてください。)
クラシックをあまり聴かないエントラントさんもいると思うので、僕が考える「交響曲を良い音で表現するための3つのステップ」を解説したい。
第一段階は、ソースに忠実な帯域バランスとサウンドステージの再現。高音域や低音域が極端に強調されたり、逆に弱くなったりすると、特定の楽器が意図しないタイミングで目立ち、楽曲の音楽的な意図が崩れてしまう。また、ステレオ再生の基本として、左右の音圧バランスを均等にすることが重要だ。(この2つはクラシック以外の全ての課題曲にも共通します)
第二段階では、オーケストラを構成する様々な楽器の質感を再現すること。金管楽器や木管楽器、弦楽器など素材が違う楽器の質感表現。また、抑揚を左右する低音楽器のリアリティや低音方向のレンジの伸びを意識すること。サウンドステージについては、第一段階で整えた全体の左右バランスに加え、高音・中音・低音それぞれの帯域ごとのバランスや質感表現を統一したい。また、オーケストラは楽器の数が多いため、機材面ではソース機器からスピーカーまでの総合的な性能(分解能やS/N比の表現力など)も大きな影響を与える。
第三段階 は、フォーカスと速度感を揃えること。これにより、オーケストラを構成する複数の楽器が混ざり合わず、サウンドステージの奥行きのレイヤー感が上がる。
続いて、この楽曲の聴きどころだが、今回は5:45 付近から再生しようと思う。最初に、小レベルの音の明瞭度やS/N感、聴感上のノイズフロアを確認し、高音域の透明感、サウンドステージの広がり、楽器の位置関係をチェックする。6:10 頃から徐々に盛り上がり、ヴァイオリンの弦の響きが際立つ。さらに 6:40 からは、ティンパニを含む打楽器が加わり、クレッシェンドへと向かう。そして 7:30 の強烈な打撃音は、上位クラスの印象を左右する重要なポイントとなる。
 |
アルバム: | Felix Mendelssohn: Symphonies No. 1 et No. 3 | ||
| アーティスト: | 山田和樹 | |||
| トラック: | Track8 : Symphonie No. 3, Op. 56 "Écossaise": IV. Allegro vivacissimo | |||
| https://www.qobuz.com/jp-ja/album/felix-mendelssohn-symphonies-no-1-et-no-3-kazuki-yamada-orchestre-philharmonique-de-monte-carlo/lwturf787cvya | ||||
 |
アルバム: | Something in the Water | ||
| アーティスト: | Jennifer Hartswick | |||
| トラック: | Track3 : Two Way Mirror | |||
| https://www.qobuz.com/jp-ja/album/something-in-the-water-jennifer-hartswick/vr474jc20iiub | ||||
 |
アルバム: | LOST CORNER | ||
| アーティスト: | 米津玄師 | |||
| トラック: | Track9 : さよーならまたいつか!- Sayonara | |||
| https://www.qobuz.com/jp-ja/album/lost-corner-kenshi-yonezu/fcvqzbtnnbpdc | ||||
 |
アルバム: | Harlequin | ||
| アーティスト: | Lady Gaga | |||
| トラック: | Track7 : sMILE | |||
| https://www.qobuz.com/jp-ja/album/harlequin-lady-gaga/ey41eb0sulr9a | ||||
 |
アルバム: | 花 | ||
| アーティスト: | 藤井 風 | |||
| トラック: | Track1 : 花 | |||
| https://www.qobuz.com/jp-ja/album/fujii-kaze/vk5js39ebxxhc | ||||
 |
アルバム: | Sing 2 (Original Motion Picture Soundtrack) | ||
| アーティスト: | U2 | |||
| トラック: | Track1 : Your Song Saved My Life (From Sing 2) | |||
| https://www.qobuz.com/jp-ja/album/sing-2-original-motion-picture-soundtrack-various-artists/e99rqx3fo58nc | ||||



















